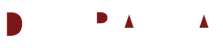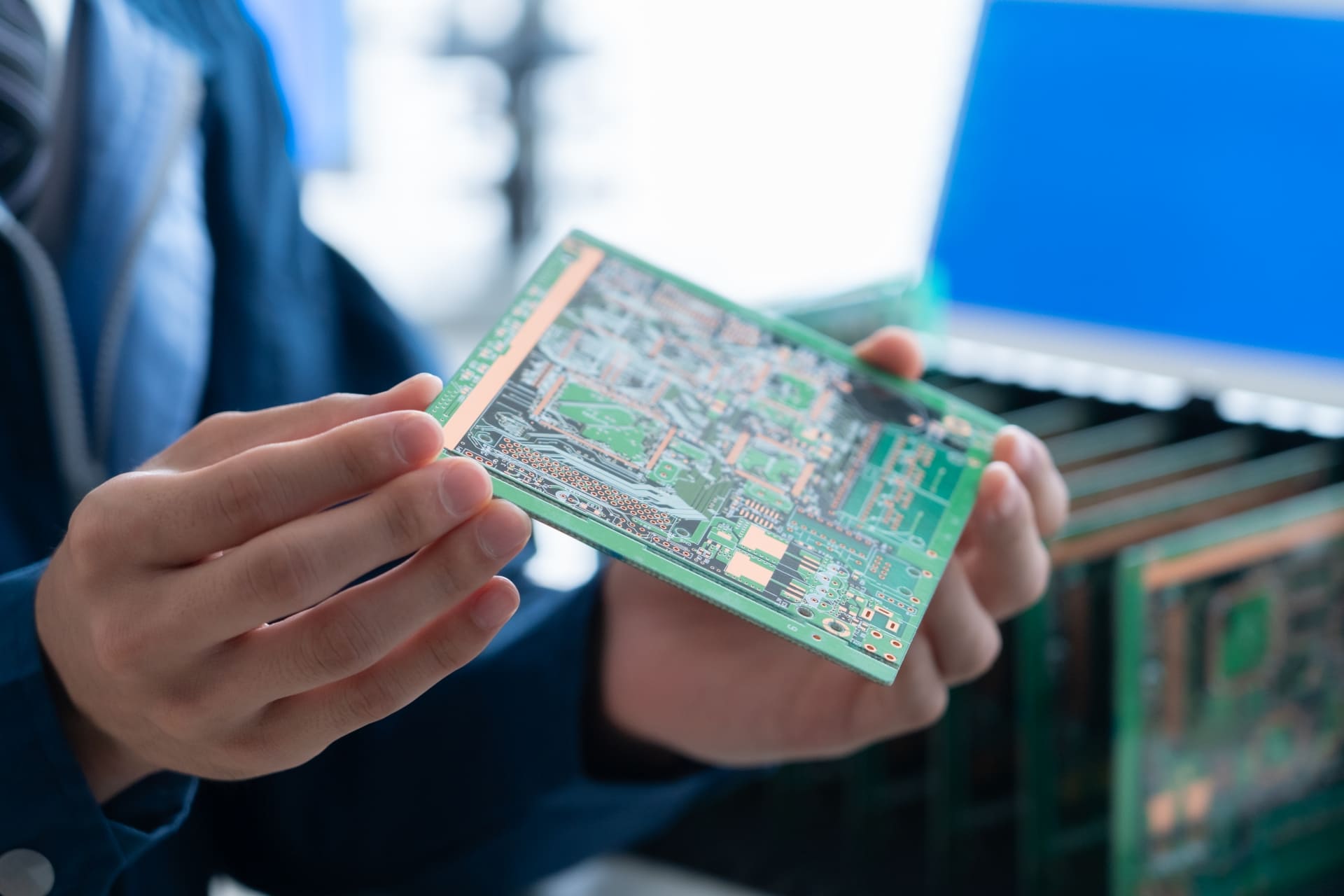ここ数年、サイバーセキュリティの世界で劇的な変化が起きています。AIによる攻撃手法が高度化する一方で、防御側でもAI技術による自動化が急速に進んでいる。
特に注目すべきは、エンドポイントセキュリティ領域でのAI活用です。従来のアンチウイルスソフトが「既知の脅威」しか防げなかったのに対し、現在のEDR(Endpoint Detection and Response)ソリューションは、機械学習により「未知の脅威」まで検出できるようになった。これは単なる技術進歩ではありません。セキュリティ運用そのものを根本的に変える革命なのです。
私が最近、複数の情報・通信業企業のIT責任者と話していて感じるのは、この変化の速度に追いつけずにいる組織が意外に多いということです。「まだアンチウイルスソフトで十分では?」と考えている管理者もいますが、実際にはランサムウェア攻撃の34%が認証情報の不正利用から始まっているという現実を見ると、従来の境界防御だけでは限界があることは明らかです。
自動化がもたらす運用効率の変革
ここで重要なのは、AI技術がもたらす「自動化」の真の価値です。単に脅威を検知するだけでなく、インシデント発生時の初動対応から復旧まで、一連のプロセスを自動化できることが画期的なのです。
例えば、化学工業の大手メーカーでは、海外工場を含む全拠点のエンドポイントセキュリティを一元管理する必要がありました。従来なら各拠点にセキュリティ専門者を配置するか、24時間体制のSOC(セキュリティオペレーションセンター)を構築する必要があったでしょう。しかし、AI駆動のEDRソリューションなら、脅威を自動検知し、即座に隔離・修復まで実行できる。
この自動化によって、人的リソースが限られた中堅企業でも、大企業レベルのセキュリティ運用が可能になります。実際、マネージドサービス事業者では、AI エージェントを活用したプレイブックベースの自動対処が大企業にも受け入れられ始めているという調査結果もあります。
考えてみてください。従来のセキュリティ運用では、アラートが発生するたびに担当者が手動で調査し、判断し、対処していました。しかし現在のAI技術なら、パターン認識により99%以上の精度で脅威を判別し、瞬時に適切な対応を実行できる。これは単なる効率化ではなく、セキュリティレベルの向上でもあります。
ゼロトラスト時代のエンドポイント戦略
テレワークの普及により、企業の境界が曖昧になった現在、エンドポイントセキュリティは最後の砦となっています。特に服飾雑貨業界のような、顧客データを大量に扱い、かつ店舗やオフィスが地理的に分散している業界では、各エンドポイントでの自律的なセキュリティ機能が必須です。
ここでも、AIによる自動化が威力を発揮します。ネットワークから切り離された状態でも、端末レベルで脅威を検知・対処できる「オフライン保護機能」。これにより、出張先や一時的なネットワーク障害時でも、セキュリティレベルを維持できるのです。
しかし、ここで批判的な視点も持つべきでしょう。多くの企業が「AI搭載」という宣伝文句に惑わされ、実際にはシンプルなルールベースのシステムを導入してしまうケースが後を絶ちません。真のAI駆動型セキュリティとは、継続学習により新たな攻撃パターンに適応し、ゼロデイ攻撃にも対応できるものでなければなりません。
日本企業が直面する現実的課題
実は、日本の多くの企業では「セキュリティ人材不足」が深刻な問題となっています。陸運業界では、M&Aにより企業規模が拡大する一方で、IT・セキュリティの専門人材が追いついていない状況です。
このような環境では、「SOCフリー」なセキュリティ運用が理想的です。AI技術により、専門知識を持たないIT担当者でも、エンタープライズレベルのセキュリティを維持できる。これこそが、AI自動化の真の価値だと私は考えています。
ただし、ここで重要なのは「完全自動化」への過度な依存は危険だということです。AIシステムも完璧ではありません。定期的な人間による監査と、継続的な学習データの更新が必要です。
未来のセキュリティ運用モデル
今後5年間で、エンドポイントセキュリティはさらなる進化を遂げるでしょう。XDR(Extended Detection and Response)により、エンドポイント、ネットワーク、クラウドを横断した統合的な脅威検知が当たり前になる。
しかし技術進歩だけでは不十分です。重要なのは、その技術を適切に活用できる「運用設計」です。AIの判断基準をどう設定するか、どの程度まで自動化を許可するか、人間の介入ポイントをどこに設けるか。これらの設計次第で、同じ技術でも効果は大きく変わります。
私の経験では、最も成功している企業は「段階的自動化」を採用しています。まず人間が判断していた作業を徐々にAIに委譲し、同時に運用ノウハウを蓄積していく。この手法により、技術導入のリスクを最小化しながら、効果を最大化できるのです。
まとめ
エンドポイントセキュリティにおけるAI自動化は、もはや「導入するかどうか」ではなく「いつ、どのように導入するか」の問題です。特に、人的リソースが限られた日本企業にとって、この技術は競争優位性を維持するための必須要素となっています。
重要なのは、単純にAI製品を導入することではありません。組織の規模、業界特性、運用体制に合わせて、適切な自動化レベルを見極めること。そして何より、技術と人間の協調により、持続可能なセキュリティ運用モデルを構築することです。
未来のセキュリティは、AIと人間が協働する新たなパラダイムの中にあります。その変化の波に乗り遅れないよう、今こそ行動を起こすべき時なのです。